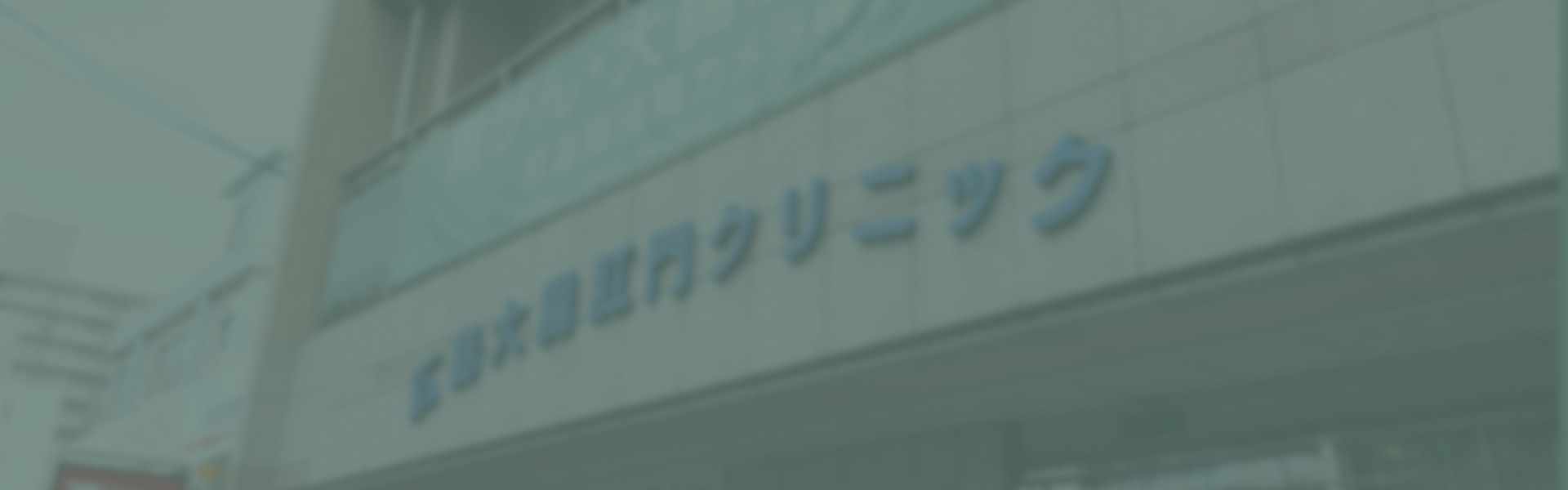
逆流性食道炎
こんな症状はありませんか?
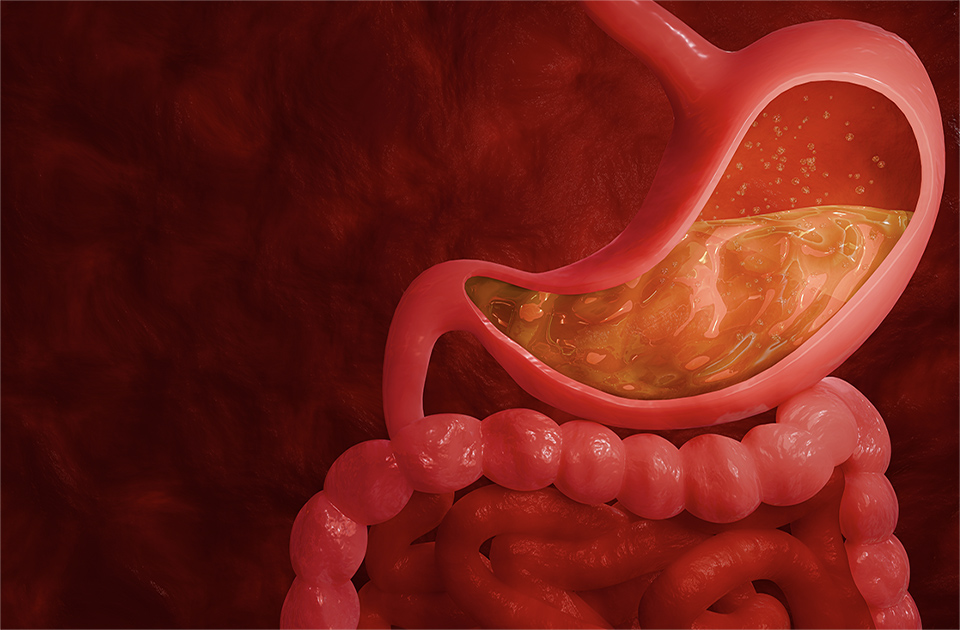
- 胸焼けや呑酸(どんさん)
- 喉の違和感
- 食べ物が詰まるような感じ
- 声のかすれ
- 胸の締め付けられるような痛み
- 咳や喘息の症状
これらの症状が続く場合、食道に炎症が起こっている可能性があります。
逆流性食道炎とは
逆流性食道炎は、胃の内容物や胃酸が食道に逆流することで、食道粘膜が傷つき炎症を引き起こす病気です。以前は日本人に少ない病気とされていましたが、食生活の欧米化や生活習慣の変化に伴い、近年増加傾向にあります。通常、食べ物は胃の中で強い酸性の胃液によって分解されます。しかし、胃酸が何らかの原因で食道に逆流すると、食道の粘膜がダメージを受け、炎症を引き起こすのです。
逆流性食道炎の原因
生活習慣の乱れ
過食や高脂肪食、早食い、飲酒、喫煙、そして食後すぐに横になることが主な原因です。特に食後すぐに横になる姿勢は、胃酸が逆流しやすくなるため注意が必要です。
下部食道括約筋の機能低下
胃と食道のつなぎ目にある下部食道括約筋が緩むと、胃酸が逆流しやすくなります。この筋肉の機能が低下することで、逆流性食道炎が起こりやすくなります。
蠕動運動の低下
胃や腸の蠕動運動には、逆流した物を胃に戻す役割があります。しかし、この働きが低下すると逆流が続き、食道に炎症が起こります。
脂肪分やタンパク質の多い食事・食べ過ぎ
脂肪分が多い食事は「コレシストキニン」という酵素を分泌し、下部食道括約筋を緩めてしまいます。また、タンパク質は消化に時間がかかるため、胃酸の逆流を引き起こすリスクが高まります。
お腹が圧迫される体型
肥満や妊娠、猫背といった姿勢が腹部に圧力をかけ、胃酸の逆流を引き起こします。
腹圧がかかる動作
締め付けの強い衣服や、重い物を持ち上げる動作、前かがみの姿勢なども腹圧を高めるため、逆流の原因になります。
加齢による機能低下
加齢により筋肉が衰えることで、下部食道括約筋や蠕動運動の機能が低下します。さらに、唾液の分泌量も減少するため、胃酸が逆流しやすくなります。
食道裂孔ヘルニア
食道と胃のつなぎ目に隙間ができることで、胃酸が食道に逆流しやすくなります。
薬の副作用
降圧剤の一部には下部食道括約筋を緩める作用があり、逆流性食道炎を引き起こすことがあります。また、ピロリ菌の除菌治療後にも発症するケースがあります。
検査と治療方法
検査方法
まず、問診で症状や日常生活について詳しく伺います。その後、胃カメラ検査で食道粘膜の状態を直接確認します。逆流性食道炎の場合、食道と胃の境目に赤みやびらんが見られることが特徴です。びらんが確認されない場合は非びらん性胃食道逆流症と診断されます。
治療方法
生活習慣の改善
以下の生活習慣を心がけることで、胃酸の逆流を防ぎます。
食生活の改善
脂肪分、刺激物、甘いものを控えましょう。
飲酒や喫煙を減らす
胃酸の分泌を促進するため控えましょう。
食後すぐに横にならない
就寝時は上半身を少し高くすることで逆流を防ぎます。
腹圧を避ける
猫背や前かがみの姿勢、締め付ける衣類を避けましょう。
便秘の改善
食物繊維や水分をしっかり摂り、適度な運動を心がけましょう。
薬物療法
胃酸分泌を抑える薬(プロトンポンプ阻害薬)を中心に、胃腸の蠕動運動を改善する薬や粘膜保護剤を症状に応じて併用します。逆流性食道炎は再発しやすいため、医師の指示に従って治療を継続することが重要です。炎症が長引くと食道がんのリスクも高まるため、注意が必要です。
再発を防ぐために
軽症の場合は生活習慣の改善のみで症状が緩和することもあります。しかし、逆流性食道炎は再発しやすい病気です。症状が改善しても油断せず、生活習慣の見直しを続け、原因を取り除くことが重要です。できることから少しずつ取り組み、症状の改善と再発予防に努めましょう。
クリニック情報
| クリニック名 | 広島大腸肛門クリニック |
|---|---|
| 住所 | 〒733-0823 広島県広島市西区庚午南1-35-21 |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-12:00 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | × |
| 14:00-18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × |
休診日:木曜午後・土曜午後・日曜祝日
●:月曜日と金曜日の午前中は手術です。
平日の午前中は、内視鏡の検査などで混み合っておりますので、
初診の方は、可能であれば平日午後にお越しください。
お問い合わせ
広島大腸肛門クリニックへお気軽にお問い合わせください。






